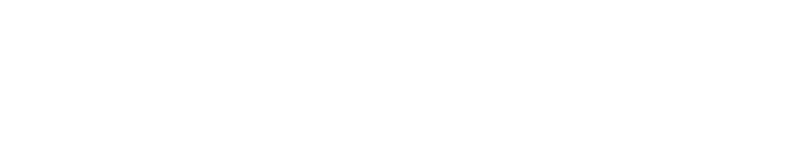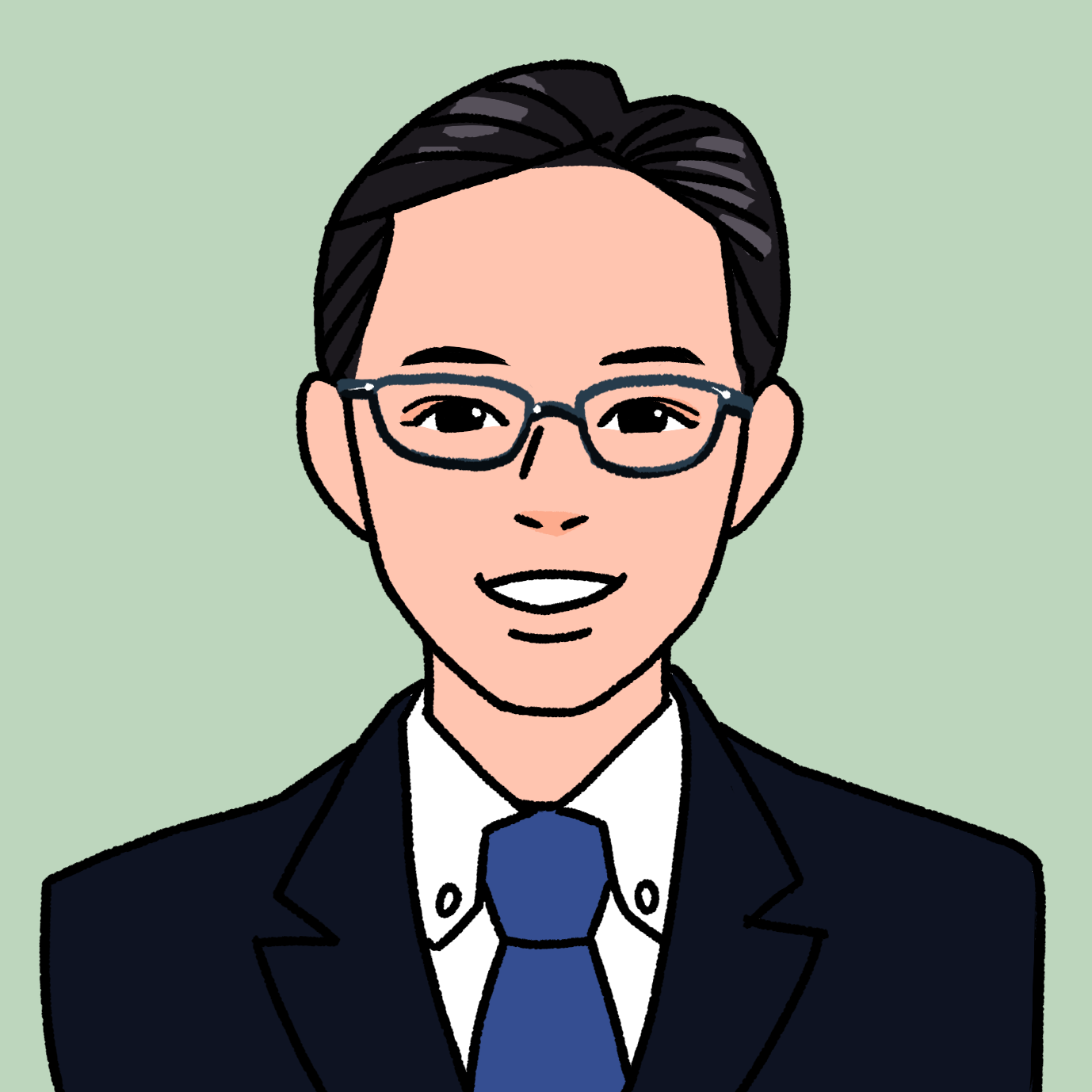中国の特許保護体制は、極めて中国的な特徴を有しており、司法保護と行政保護の両面から構成されている。行政保護には、各地方知識産権局による特許保護に加え、知的財産の海関(税関)保護も含まれる。
中国では、司法保護と行政保護が並行して機能する仕組みが採用されており、特許侵害紛争において、特許権者または利害関係者は、人民法院に訴えを提起することも、特許管理部門に処理を求めることも可能である。
また、越境する貨物の輸出入において知的財産侵害が疑われる場合、中国海関は法律に基づき、差押え、押収、没収などの行政措置を講じ、知的財産権を侵害する貨物の出入りを禁止することができる。
目次
特許無効宣告請求の審理
一、人民法院(司法保護)
(一)組織構造
人民法院は、特許司法保護の中核的機関である。
中国の人民法院は、以下の四つの階層に分かれている:
最高人民法院、高級人民法院、中級人民法院、基層人民法院である。
このほかに、軍事法院、海事法院、鉄道輸送法院、知的財産法院といった専門法院も設置されている。人民法院は主に《人民法院組織法》に基づき、組織・運営されている。
最高人民法院は北京市に設置されており、中国の最高審判機関である。
最高人民法院が審理する事件は以下のとおりである。
- 法律や法令でその管轄と定められた第一審事件、および最高人民法院が審理すべきと判断した第一審事件
- 高級人民法院または専門人民法院による判決・裁定に対する上訴・抗告事件
- 最高人民検察院が審判監督手続に基づき提起した抗告事件
高級人民法院は省・自治区・直轄市に設置されており、それぞれの行政区域における最高裁判機関である。現在、中国本土には31の高級人民法院が存在している。
高級人民法院が審理する事件は以下のとおりである。
- 法律・法令によりその管轄とされる第一審事件
- 下級人民法院が移送した第一審事件
- 下級人民法院の判決・裁定に対する上訴・抗告事件
- 人民検察院が審判監督手続に基づき提起した抗告事件
中級人民法院は、省および自治区内の地区、設区市、自治州、直轄市に設置されている。
中級人民法院が審理する事件は以下のとおりである。
- 法律・法令でその管轄と定められた第一審事件
- 基層人民法院が移送した第一審事件
- 基層人民法院の判決・裁定に対する上訴・抗告事件
- 人民検察院が審判監督手続に基づき提起した抗告事件
中級人民法院は、自らが受理した刑事・民事事件のうち、重要であり上級人民法院による審理がふさわしいと判断した場合には、対応する高級人民法院への移送を求めることができる。
基層人民法院は、県、県級市、自治県、市轄区に設置されている。原則として、基層人民法院は刑事および民事の第一審事件を審理する。ただし、法律・法令で別途定められた事件はこの限りではない。重大案件については、中級人民法院への移送を申請することができる。
特許侵害事件の第一審は、通常、最高人民法院が指定した管轄権を有する知的財産法院または中級人民法院によって審理される。損害賠償請求額が特に高額な重大事件については、高級人民法院が第一審を行うことも可能である。
(二)知的財産法院と知的財産法廷の現状
1.知的財産法院
知的財産の審判効率と質の向上、保護水準の引き上げを目的として、中国の裁判体系内に専門の知的財産法院を設立する必要性が年々高まっていた。これを受け、2014年8月31日、第12期全国人民代表大会常務委員会第10回会議において「北京・上海・広州に知的財産法院を設立する決定」が採択され、3都市に知的財産法院が設立された。
知的財産法院の設立目的は以下のとおりである。
- 知的財産の司法基準の統一
- 審判資源の集約と効率化
- 保護主義の排除
- 民事・行政・刑事の知的財産審判制度の体系的整理
- 国際的な知財保護潮流への適応
北京・上海・広州が選ばれた理由は、以下のような代表性および審理能力の高さにある。
- 北京には国家知識産権局、国家工商行政管理総局商標局、国家版権局などが所在し、これらの決定に関連する行政訴訟案件が多い。
- 上海は直轄市であり、国際経済・金融・貿易・海運の中心として代表性がある。
- 広州は中国経済で最も活力のある広東省の省都であり、他の省・自治区との行政構造が同様であるため、代表性がある。
それぞれの法院の組織構成は以下のとおりである。
- 北京知的財産法院:立案庭、審判第一庭、審判第二庭、審判監督庭、総合事務室、技術調査室、司法警察支隊の7部門を有する。
- 上海知的財産法院:上海市第三中級人民法院と合同で業務を行っており、審判一庭、審判二庭、技術調査室の3部門を有する。他の事務(立案・執行・管理等)は第三中級人民法院が担っている。
- 広州知的財産法院:立案庭、特許審判庭、著作権審判庭、商標・不正競争審判庭、総合事務室、技術調査室、司法警察支隊の7部門を設置している。
知的財産法院の裁判官の任免については、次のように規定されている。
- 院長は所在地の市人民代表大会常務委員会主任会議が提案し、同級人民代表大会常務委員会が任免する。
- 副院長・庭長・裁判官・審判委員会委員は、同法院の院長が所在地の市人民代表大会常務委員会に提案して任免される。
- 最高人民法院は三都市の知財法官の選任基準について指導的見解を示すものとされている。
2020年9月には、海南自由貿易港知的財産法院が新たに設立され、中国で4番目の知的財産法院となった。これは、2019年に国務院国資委、最高人民法院、最高人民検察院、海南省人民政府が共同で発表した「海南自由貿易試験区および自由貿易港建設支援に関する意見」に基づくものである。
知的財産法院の第一審管轄権は以下のとおりである:
- 知的財産法院が所在する省(直轄市)内において発生した、特許、植物新品種、集積回路配置設計、営業秘密、コンピュータソフトウェア、著名商標の認定、独占禁止に関する民事・行政事件(第一審)。
- 北京市知的財産法院はさらに、国家知識産権局特許復審・無効審理部(旧特許復審委員会)、国家商標局、国家版権局が下した決定・裁定に対して不服申立てがなされた行政授権・確定事件の第一審も管轄する。
- 知的財産法院所在都市の基層人民法院が受理した第一審の知財事件について、知的財産法院での審理が必要と判断される場合は、当該法院に報告し審理を依頼することができる。
- 知的財産法院は、その所在都市の基層人民法院が管轄する重大な対外性や影響力を有する第一審知的財産事件について、民事訴訟法第38条および第39条に基づき、裁量で引き上げ審理することができる。
- 知的財産法院が第一審判決・裁定を下した事件の控訴事件は、当該法院所在地の高級人民法院が審理する。
- 当該省(直轄市)内の第一審知的財産民事事件のうち、法律や司法解釈によって知的財産法院が管轄すべきと明示されていない事件については、基層人民法院が管轄する(訴額の制限を受けない)。
- 知的財産法院は、当該都市の基層人民法院が下した第一審の著作権、商標、技術契約、不正競争に関する民事・行政判決・裁定の控訴事件も審理する。
知的財産法院設立の背景とその効果
北京、上海、広州および海南に設置された知的財産法院は、中国における知的財産司法制度改革の一環として、特許等の技術系知財事件に関する省(直轄市)内での集中管轄という試みである。
これにより、地域を超えた審判資源の統合や、事件審理の経験蓄積が進み、知的財産法院の職能が強化された。
北京・上海・広州の知的財産法院は設立以降、業務を着実に展開してきた。特に、北京知的財産法院は2022年において、33,750件の事件を受理し、23,757件を結審しており、設立当初の3倍を超える件数となっている。
上海知的財産法院も同様に、2022年には5,487件の事件を受理し、前年と比べて1.01%の増加を示した。中でも、特許権事件は3,832件で全体の約70%を占め、前年より7.94%増加している。
インターネット関連知財事件も顕著に増加し、4,505件(前年比31.8%増)で、全体の82.1%を構成している。
審理対象技術は、モバイルチップ、生物医薬、データシステム、ナビゲーション機器、新素材など先端分野に及び、専門性の高さと法的複雑性、審理難易度の高さが特徴である。
2.知的財産法廷
北京・上海・広州の知的財産法院の設立および運用が良好な成果を収めたことを受け、2017年1月以降、最高人民法院は全国各地における知的財産法廷の設置を段階的に承認した。
第1陣の知的財産法廷は2017年に設立され、「最高人民法院が南京市、蘇州市、武漢市、成都市の中級人民法院において、専門審判機関を設けて一部の知的財産事件を越境管轄することを承認する通知(法〔2017〕2号)」に基づき、南京、蘇州、武漢、成都の各中級人民法院内に、知的財産審判庭(法廷)が設置された。
これら4都市が初期設置地に選ばれた理由は、経済発展と技術革新能力が高く、知的財産事件の件数が多いこと、また知財審理の人材が比較的充実していることによる。
例えば、江蘇省には2.9万社以上の特許出願企業があり、73社が国家知的財産モデル企業または優良企業に選出され、全国最多である。また、2016年に江蘇省で受理された特許事件は6,390件に上り、件数は全国上位である。
2017年から2022年にかけて、成都、南京、蘇州、武漢に続き、合肥、杭州、寧波、福州、済南、青島、深圳、西安、天津、長沙、鄭州、南昌、長春、蘭州、厦門、烏魯木斉、景徳鎮、重慶、瀋陽、温州、無錫、徐州などの都市にも知的財産法廷が次々に設置され、合計26か所に達した。
これらの知的財産法廷はすべて、所在地の中級人民法院に内設された機関であり、地域を越えた専門性の高い知的財産事件を集中して審理する役割を担っている。ただし、独立した裁判所ではなく、あくまで中級人民法院の下部機関である。
知的財産法廷の設立背景と意義
全国各地の経済が急速に発展し、イノベーション活動が活発化するにつれ、知的財産紛争の件数も増加している。この状況に対応するため、専門審判機関のニーズが高まり、各地における知的財産法廷の設立が進められた。
地方に知的財産法廷を設置することにより、優れた審理資源の集中と、紛争処理の効率と質の向上が期待される。これは各地のイノベーション環境に対し、強力な司法支援を提供し、経済発展の促進にもつながる。
各地の知的財産法廷が管轄する事件は以下のとおりである:
- 指定された管轄区域内で発生した、特許、植物新品種、集積回路配置設計、営業秘密、コンピュータソフトウェア、著名商標認定、独占禁止に関する民事・行政第一審事件。
- 所在市内で発生した、商標、著作権、不正競争、技術契約紛争などに関する第一審の民事・行政事件。
- 同じく市内で発生した第一審の知的財産民事・行政・刑事事件に関する、基層人民法院の判決・裁定に対する控訴事件。
知的財産法廷は中級人民法院に所属しているが、その管轄範囲は必ずしも所属中級人民法院の地域に限定されず、行政区域を越えて事件を管轄することができる。
省内に複数の知的財産法廷が設置されている例
経済がより活発で、知的財産活動も盛んな一部の省では、複数の都市に知的財産法廷が設置されており、省都にある知的財産法廷の管轄範囲は他の都市と異なる構成をとる場合がある。
例えば、浙江省には杭州(省都)、寧波、温州に知的財産法廷が設置されている。
- 杭州知的財産法廷の管轄範囲は、杭州市、湖州市、衢州市である。
- 寧波知的財産法廷は、寧波市、嘉興市、紹興市、台州市、舟山市を管轄する。
- 温州知的財産法廷は、温州市、金華市、麗水市を管轄する。
また、江蘇省には南京(省都)、蘇州、無錫、徐州に知的財産法廷が設置されている。
- 南京知的財産法廷は、南京市、鎮江市、揚州市、泰州市、塩城市、淮安市を管轄する。
- 蘇州知的財産法廷は、蘇州市、常州市、南通市を管轄する。
- 徐州知的財産法廷は、徐州市、宿遷市、連雲港市を管轄する。
- 無錫知的財産法廷は、無錫市のみを管轄する。
山東省、江蘇省、福建省などでも、同様に複数の知的財産法廷が設置され、それぞれ異なる地域的な管轄構成が取られている。
知的財産法院と法廷の比較
上記の26の中級人民法院に内設された知的財産法廷は、北京・上海・広州・海南に設置された4つの知的財産法院とともに、越境管轄権を一定範囲で有している。
両者の違いは以下のとおりである:
- 知的財産法廷は各地の中級人民法院内に設置された機関であり、中級人民法院の一部門としての位置付けである。
- 一方、4つの知的財産法院は中級人民法院として独立した組織体である。
また、管轄範囲に関しても違いがある。
- 知的財産法廷の越境管轄範囲は、省全体をカバーするものもあれば、特定の複数都市に限定される場合もある。
- 一方で、知的財産法院の越境管轄は、原則としてその省(または直轄市)全域を対象とする。
したがって、知的財産事件の管轄範囲という点においては、知的財産法院の方が、各法廷よりも広範である。
特許侵害事件の管轄構造の変遷と展望
知的財産制度の発展と、知的財産事件の件数の増加に伴い、特許侵害訴訟を管轄する人民法院の構造は、分散から集中へと移行してきた。
かつては、特許侵害第一審事件の管轄は、各省・自治区・直轄市政府所在地の中級人民法院に限定されていた。その後、最高人民法院の指定により、非政府所在地の中級人民法院や、特定の基層人民法院(例:義烏市人民法院)にも管轄権が拡大された。
しかし、管轄権を持つ人民法院が増えたことで、同一案件で異なる裁判所が異なる判決を出す状況が生じた。これを是正するため、知的財産法院・法廷を通じて、特許訴訟事件の管轄を集中させる方向に舵が切られたのである。
3.最高人民法院知的財産法廷
2019年1月1日より、最高人民法院知的財産法廷(以下、最高院知財法廷)が正式に発足し、特定の知的財産事件の控訴審を専門に担当することとなった。
最高院知財法廷が審理を担当する事件は、以下のとおりである:
- 各地の高級人民法院、知的財産法院、中級人民法院が下した
発明特許、実用新案特許、植物新品種、集積回路配置設計、営業秘密、コンピュータソフトウェア、独占禁止に関する第一審民事事件の判決・裁定に対する控訴事件。 - 上記の各法院が下した
発明特許、実用新案特許、植物新品種、集積回路配置設計に関する特許授権・確定行政事件の第一審判決・裁定に対する控訴事件。 - 上記の各法院が下した
営業秘密、ソフトウェア、独占禁止等の行政処分に関する第一審行政事件の判決・裁定に対する控訴事件。
以上のように、最高院知財法廷は、技術性および社会的影響の大きい知的財産事件の控訴審を一元的に審理するために設けられた最高裁レベルの専門部門である。
なお、人民法院における特許侵害訴訟の管轄に関する詳細は、第4章第2節「訴訟管轄」に規定されている。
二.国家知識産権局と地方知識産権局(行政保護)
中国の《特許法》第3条により、中国の特許行政管理体制は二層構造とされている。
- 一つは、**国務院直属の特許行政部門(通常、国家知識産権局と呼ばれる)**である。
- もう一つは、**各省・自治区・直轄市の人民政府に属する地方の特許管理部門(地方知識産権局)**である。
特許に関する行政保護は、特許行政管理部門によって実施される。現行《特許法》では、地方知識産権局が特許の行政執行業務を担い、特許侵害紛争の処理や、模倣特許の取り締まりなどを行うことが明記されている。
国家知識産権局の制度改革
2018年以前、国家知識産権局(CNIPA)は国務院直属機関であり、特許業務の主管機関として、対外知的財産関連業務の総合調整も担当していた。
同局の下には「特許局」および「特許復審委員会」などの下部組織が設置されており、
- 特許局は特許出願の受理、審査、権利付与を担当していた。
- 特許復審委員会は、特許出願の再審および特許無効宣告請求の審理を担当していた。
なお、地方知識産権局は国家知識産権局の直属機関ではなく、地方政府の下に属するが、業務面では国家知識産権局から指導を受ける体制となっていた。
地方知識産権局は、以下のように三層構造で組織されている。
- 省・自治区・直轄市レベルの知識産権局
- 設区市(市レベル)に属する知識産権局
- 県・区レベルの知識産権局
2018年の改革
第13期全国人民代表大会第1回会議において、国務院の機構改革案が可決され、国家市場監督管理総局(SAMR)が新たに設立された。
これにより、以下の機関の職能が統合された:
- 国家工商行政管理総局
- 国家質量監督検査検疫総局
- 国家食品薬品監督管理総局
- 国家知識産権局
- 国家発展改革委員会の価格監督・独占禁止執行職能
- 商務部の経営者集中審査職能
- 国務院反独占委員会弁公室の機能
これに伴い、国家知識産権局は、国家市場監督管理総局の下部機関に再編された。再編後の国家知識産権局は、旧知識産権局の職能に加え、
- 商標管理業務(旧工商総局より)
- 原産地地理標章の管理(旧質検総局より)
も統合された。
さらに、特許復審委員会は、国家知識産権局の内部部門である「特許局復審・無効審理部」へと改称・再編された。
2023年の改革
2023年3月、第14期全国人民代表大会第1回会議において、新たな国務院機構改革案が可決され、国家知識産権局は再び国務院直属機関に復帰することとなった。
この改革には以下の意義がある:
- 国家知識産権局の行政機構内における地位の格上げ
→ 知的財産政策の国家戦略的推進におけるリーダーシップ強化 - 管理体系の簡素化と部門間連携の強化
→ 縦の効率化・横の協調化による管理能力の向上 - 特許・商標の質的向上にリソースを集中させるための体制整備
ただし、特許・商標に関する現場での執行職能は依然として各地の市場監督管理局に残されており、国家知識産権局はその業務に対して指導的役割を果たすものとされている。
同局は、
- 侵害判定基準の制定・指導
- 検査・鑑定体制の整備
- 全国統一の執行メカニズムの構築
などを通じて、全国的な知的財産保護体制の質を高めている。
制度の変遷のまとめ
過去数十年にわたり、知的財産行政管理体制は、国家科委の傘下にあった特許局から独立機関への移行、さらに市場監管総局への編入、そして再び国務院直属機関への復帰という変遷をたどってきた。
現在の体制においては、特許と商標の管理が統一的に一元化されており、知的財産管理体制の最適化と明確化が進められている。
三.知的財産の海関保護(税関による保護)
知的財産の海関保護とは、法律に基づき、中国海関が国境において、商標権、著作権、特許権などの知的財産権の侵害行為を取り締まる制度である。
貨物の輸出入に関する知的財産権の管理と保護は、中国海関が担当する。
輸入貨物の荷受人またはその代理人、輸出貨物の荷主またはその代理人は、輸出入に係る知的財産権の状況について、海関に対して誠実に申告し、関連証明書類を提出しなければならない。
海関は、中国の法律や行政法規によって保護される商標権、著作権、その関連権利および特許権について、差押え、押収、禁輸措置などを講じることができる。
また、権利者が海関に対して事前に申請を提出することで、積極的な保護措置の実施を依頼することも可能である。